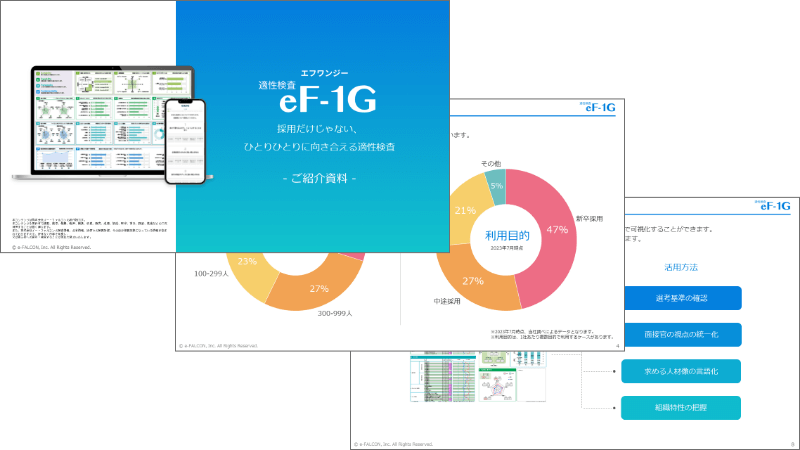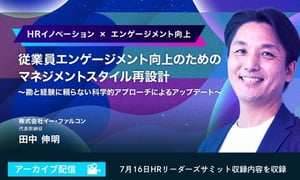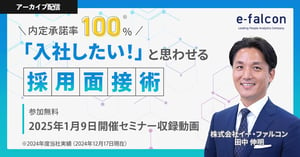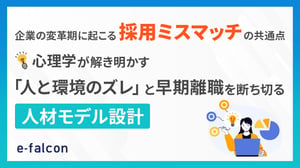中途採用は見極めが重要!中途採用の見極めの落とし穴と成功のポイント
「中途採用で見極めがうまくいかず、戦力になるまでに時間がかかった」「期待していたほどの成果が出ない」といったお悩みを抱えていませんか?
中途採用での人材の見極めには、新卒採用とは異なる視点が求められます。
即戦力として期待される中途採用者の見極めに失敗すると、企業の競争力の低下にもつながりかねません。
中途採用の見極めが重要な理由や注意したい落とし穴、中途採用の見極めから成功のためのポイントなどを詳しく解説します。
中途採用で見極めが重要な理由
労働市場の流動化や働き方の多様化により、転職があたり前の世の中になりました。企業においても、中途採用は人材戦略の重要な選択肢の1つです。
リクルートワークス研究所の「中途採用実態調査 2023年度実績」によれば、約8割の企業が中途採用を実施しています。
新卒採用が企業の未来を担う人材を育成する長期的な視点であるのに対し、中途採用は、特定のスキルや経験を持つ人材を迅速に確保し、事業課題の解決や新たな事業展開を加速させる目的で行われることが大半です。即戦力としての期待が大きい分、失敗したときの影響も大きくなります。
まずは、中途採用での人材の見極めが重要な理由を見ていきましょう。
参考:リクルートワークス研究所|中途採用実態調査 2023年度実績
即戦力として短期間で成果を発揮してもらう必要があるから
中途採用者に対する企業の期待は、新卒採用者とは大きく異なるものです。
中途採用では新卒採用のように数年かけて育成する時間的余裕はなく、入社後すぐに戦力として活躍することが求められます。しかし、業界経験が長く優秀な履歴を持つ人材であっても、必ずしも自社で活躍できるとは限りません。
前職のやり方に固執して力を発揮できなかったり、新たな環境に馴染めなかったりするリスクも存在します。そのため、スキルや経験だけでなく、新しい環境への適応力や柔軟性も的確に見極めることが重要です。
採用コストが新卒採用よりも高く失敗時の損失が大きいから
就職みらい研究所が公表した「就職白書 2020」によると、中途採用の1人あたりの平均採用コストは103.3万円と、新卒採用の93.6万円に比べて10万円ほど高い結果となっています。
中途採用の採用コストが高額になるのは、求人広告費や人材紹介会社に支払う手数料などが主な要因です。もし見極めに失敗し、早期離職やパフォーマンスの低下などの事態に陥れば、かかった採用コストが無駄になってしまいます。
それだけでなく、再度採用活動を行うための追加コストや、その間に発生した機会損失も無視できません。このような失敗が続けば、企業に大きな経済的損失を与えることになるでしょう。
既存メンバーに与える影響が即座に現れるから
数ヶ月の研修期間がある新卒採用と異なり、中途採用者は入社後すぐに業務の現場に配属されるため、その影響は即座に現れます。
優秀な人材を採用できれば、チーム全体のモチベーション向上や知識・スキルの共有による相乗効果が期待できるでしょう。
一方で、スキル不足や協調性に欠ける人材を採用してしまうと、既存メンバーの業務負荷増加や士気低下を招き、ひいては優秀な人材の流出につながりかねません。
このような負の影響を防ぐためにも、慎重な見極めが重要です。
中途採用での見極めに失敗する企業が陥りがちな落とし穴
どの企業も中途採用で優秀な人材を獲得しようと努力していますが、なぜ見極めの失敗が起こるのでしょうか。
中途採用での見極めに失敗する企業が陥りがちな落とし穴について確認していきましょう。
経歴やスキルだけで判断してしまう
履歴書や職務経歴書に記載された華やかな経歴や資格に目を奪われ、表面的な情報だけで採用を決定してしまうことです。
しかし、経歴やスキルは候補者の能力の一側面に過ぎません。
重要なのは、それらのスキルを自社の環境でどのように活かせるか、成果に結びつけられるかです。
経験やスキルが豊富な人でも、転職先の企業に対する想いや業務に対する熱意がなければ、活躍は難しいでしょう。
社風・カルチャーへの適合性を軽視してしまう
自社の社風やカルチャーへの適合性を軽視してしまうことです。
どんなに優秀な人材でも、企業の社風やカルチャー(企業文化)に適合できない人材は、早期離職やメンバーとの摩擦を招く可能性が高まります。
例えば、チームワークを重視する社風の企業に、個人主義が強い人材を採用した場合、周囲と協調できずにパフォーマンスを十分に発揮できないでしょう。
社員同士がうまく関係を築けない状況が続くと、中途採用者だけでなく、既存社員の離職にもつながるリスクがあります。
面接官によって評価基準にバラつきがある
面接官が異なる評価基準で候補者を判断してしまうことです。
このような状況では、面接官の主観的な印象や個人的な好みが評価に影響し、客観的で公正な判断ができなくなります。
ある面接官はスキルを重視し、別の面接官は人物像を重視するといった評価基準のズレは、結果として求める人物像と異なる人材の採用につながりかねません。
その結果、ミスマッチが発生して早期離職や期待した成果が得られないリスクが高まります。
現場との連携不足により求める人物像にズレがある
人事部門と現場部門の間で、求める人物像に対する認識のズレが生じることです。
現場が本当に求めているスキル・経験と、人事部門が想定している人物像にズレが生じると、入社後にミスマッチが発生しやすくなります。
例えば、人事部門では「リーダーシップ経験」を重視して採用を進めたものの、現場では「専門的な技術スキル」をより重要視していたというようなケースです。
このような現場との連携不足は、中途採用者と現場の双方にとって不幸な結果をもたらします。
中途採用での見極めのポイント
中途採用で見極めの失敗を防ぐためには、どのようなことに注意して中途採用にあたれば良いのでしょうか。
中途採用での効果的な見極めのポイントを見ていきましょう。
職務経歴書・履歴書の深掘り
書面上の「職務経歴書・履歴書」は、候補者のキャリア概要を示すにすぎません。
記載内容を鵜呑みにするのではなく、その背景にある具体的なエピソードや困難に直面した際の対応、成果を出すまでのプロセスなどを深掘りすることが重要です。
また、転職理由も表面的な回答だけではなく、真の動機や将来のキャリアビジョンを確認することで、候補者の仕事に対する価値観を把握できます。
これにより、真の実力を見極めることにつながるでしょう。
候補者の「本質」を見抜く面接設計
効果的な面接設計には、候補者の本音や本質的な部分を引き出すための工夫が必要です。
本質的な能力や人間性を見抜く面接手法の1つに、過去の行動から将来の行動を予測する「行動面接(STAR面接)」があります。
候補者の具体的なエピソードに対し、「そのとき、何を優先し、なぜそう判断したのか?」「他メンバーと意見が対立したときにどう対応したか?」などの深掘り質問で思考や価値観を探ります。
これにより、実務での判断基準や対人スキルなどの把握が可能です。
求める人物像・評価基準の明確化
採用成功の前提となるのが、求める人物像と評価基準の明確化です。
職種やポジションに応じて、必要なスキルや経験、能力を具体的に定義し、それぞれに対して明確な評価基準を設定します。
評価項目は「Must(必須)」「Want(歓迎)」「Better(あればよい)」「Negative(不要)」に分類し、優先順位を明確にして採用に関わるすべてのメンバーで共有しておきましょう。
これにより、評価のブレを防ぎ、客観的かつ公平な見極めが可能になります。
現場社員・チームとの連携強化
中途採用の成功には、人事部門と配属予定の現場部門の密接な連携が不可欠です。
採用要件の策定段階から現場責任者やチームメンバーを巻き込み、実際の業務内容や求められるスキルレベルを正確に共有しておきましょう。
また、面接プロセスにも現場社員を参加させることで、技術的な専門性や実務能力をより正確に評価することが可能です。
現場社員が候補者と直接交流する機会を設けることで、入社後のミスマッチを最小限に抑えることにつながります。
中途採用での見極めに有効なアプローチ
実際の選考プロセスにおいて、より精度の高い見極めを実現するためにはどうすればいいのでしょうか。
中途採用での見極めに有効なアプローチについて確認していきましょう。
現場責任者を含めた複数回面接と多角的評価
1回の面接だけでは候補者の正確な評価は困難です。
複数回の面接を実施し、それぞれ異なる観点から評価を行うことで、より客観的で総合的な判断が可能になります。
例えば、一次面接では人事担当者が基本的な適性や志望動機を確認し、二次面接で現場責任者が専門性や実務能力を評価、最終面接では経営層が組織適合性や将来性を判断するというような役割分担が効果的です。
最終的には、各面接官の評価を共有して合否判定会議を行うことで、公平かつ網羅的な判断が可能になります。
カルチャーフィットを測る質問・ケース面接
社風やカルチャーへの適合性を測るためには、それに特化した質問や面接手法を取り入れることが有効です。
例えば、「チームで意見が対立した場合、どのように解決しますか」「理想的な職場環境を教えてください」などの質問を通じて、候補者の価値観や仕事観を探ります。
また、実際の業務で起こりうる状況を想定したケース面接の実施により、問題に対するアプローチ方法や論理的思考力、コミュニケーション能力を確認できます。
これにより、スキルだけでなく、企業の価値観や働き方に対する適合性を評価することが可能です。
適性検査(性格診断・能力テスト)の活用
書類選考や面接だけでは見極めきれない候補者の潜在的な特性や能力を客観的に把握するためには、適性検査の活用も有効です。
性格診断では、候補者のパーソナリティやストレス耐性、協調性などを把握でき、能力テストでは、基礎的な学力や論理的思考力、言語能力などを測定できます。
適性検査の結果は面接での印象を補完し、より客観的で多面的な評価に役立ちます。
ただし、適性検査の結果は参考情報として活用し、最終的な判断は面接や書類審査と組み合わせて総合的に行うことが重要です。
中途採用での見極め精度を高めるなら適性検査「eF-1G」
中途採用での人材の見極めは、企業の将来を左右する重要な判断です。
候補者のスキルや経験だけでなく、パーソナリティや潜在能力などの「見えにくい部分」の客観的な把握がミスマッチを防ぎ、長期的に活躍できる人材を獲得する上で重要となります。
中途採用での見極め精度をさらに高めるなら、適性検査「eF-1G」をご検討ください。
eF-1Gは、心理学・統計学・比較文化学などの分野の専門家監修のもとに開発された、就活生や転職者1人ひとりのポテンシャルを把握するための適性検査です。
「性格検査」と「能力テスト」の2種類で構成され、面接だけでは見抜けない候補者の本質的な特性を客観的に測定します。
採用部門の責任者・担当者様が自信を持って採用判断を下せるよう、「eF-1G」は強力にサポートいたします。
中途採用の見極めに適性検査の利用をご検討であれば、まずはお気軽にeF-1Gについてご相談ください。