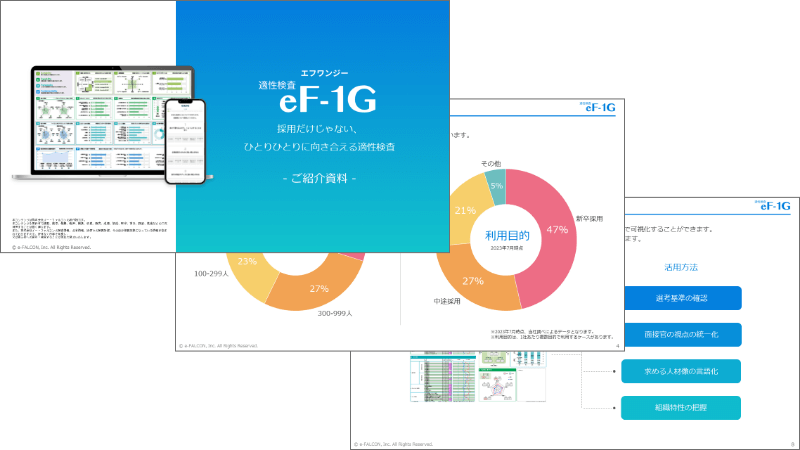「公平に評価している」つもりでも…人間につきまとう「認知バイアス」はどうすれば除去できる?
採用活動や人事評価にあたって、担当者としては「公平に」判断したいところです。
しかし、評価するほうもまた人間であり、人間である以上、完璧はありません。
特にやっかいなのが、人間につきまとう「認知バイアス」です。
誰かをひいきしているわけではない、冷静に見ているはずだ、と面接する方がどれだけ考えていても、判断がおのずと偏ってしまう。
その原因になる「認知バイアス」には、実にさまざまな種類があります。
「良い印象だったのに採用・起用してみたらそうでもなかった」という結果になったり、逆に真に優秀であることを見いだせなかったり…
そのような事態を避けるために、認知バイアスの種類について知り、克服方法を考えてみましょう。
スポーツマンの「タフ」について考える
「さすがスポーツマンだけあって、長時間勤務もこなすタフで責任感の強い人だ」。
日常生活では、非難されることはない発言かもしれません。
しかし、人事担当として評価を下すとき、これは正しいと言えるでしょうか?
人事担当者が採用にあたってこのようなイメージで面接にあたる。実はその時点で「認知バイアス」が大きく働いているのです。
「論理的錯誤」というバイアス
じつは、この発言には「論理的錯誤」という認知バイアスがかかっています。
このようなものです。
評価者が、自らの理屈で勝手に評価ルールを作り上げてしまい、そのルールで評価してしまうミス。例えば、『知識の豊富な人は理解力を備えている』や『残業時間の多い人は責任感が強い』と勝手な評価ルールを信じてしまう場合がある。
<引用:「大津市 人事評価実施要領」総務省資料>
https://www.soumu.go.jp/main_content/000611732.pdf p46
冒頭の発言には、少なくとも二重の「論理的錯誤」が働いています。
・「スポーツマン=タフ」:体力や忍耐力はあるかもしれません。しかしスポーツでのタフさがビジネスでのタフさに比例するという確証はあるでしょうか?体力がビジネスの全てでしょうか?
・「長時間勤務=責任感」:本当に「責任感」でしょうか?ただ「仕事が遅いだけ」かもしれません。
もちろん、スポーツマンに対するこうした認識が全て間違いとは言えません。しかし勝手なイメージで相手を評価していないか?それを一度疑う必要もあるのです。
驚くほど多い認知バイアスの種類
では、先ほど引用した総務省の資料で紹介されている、他のバイアスの数々をご紹介しましょう*1。
1)メイキング
評価者があらかじめ被評価者の点数や順番を決めておき、それに合わせて点数を逆算しそれぞれの評価要素の点数を調整してしまうこと。
評価者が付けた評価結果により被評価者の給与や処遇に影響が及ぶことを気にするあまり被評価者に不利益が生じないよう評価結果とあらかじめ公表されている人事・給与への反映基準等を比較し、評価結果に手を加えてしまうケースなどが典型的な例。また、複数の被評価者を評価する際にあらかじめそこに順番を決めておき、その順番になるよう点数調整することも「メイキング」に含まれる。
2)ハロー効果
「ハロー」とは「後光」の意味で、何かひとつでも良い又は悪いとすべてが良く又は悪く見えてしまうミス。
3)イメージ評価
評価者が被評価者に対して持っている先入観やイメージだけで評価してしまうミス。
例えば、「A君は以前から豊富な知識のもとですばらしい成果を上げてきた。だから当然今期も高い成果を上げたはずだ。」と思い込み高い評価を付けてしまうケースなど。
4)寛大化傾向
実際よりも甘い評価をしてしまうミス。
例えば、『特に大きな問題もなかったんだから「特に良好」にしておこう』といった無責任な評価や『高い評価をつけておけば部下から文句も出ないだろう』といった事無かれ主義の評価、『一生懸命やっているのだから良い評価を付けてやれば喜ぶだろう』といった温情主義的な評価などがその原因となる。
5)中心化傾向
評価段階の中央値(総合評価「B」)に評価が集中してしまうミス。
「寛大化傾向」と同様、無責任な評価や事無かれ主義の評価などがその原因となる。
6)極端化傾向
評価段階の極値(総合評価「S」又は「D」)に評価が集中してしまうミス。「中心化傾向」を意識しすぎて、それを避けるために無理に「○か×か」「白か黒か」を付けようとすることがその原因となることもある。
7)対比誤差
評価者自身を評価基準として、被評価者を自分と比較して評価してしまうミス。
評価者が被評価者の担当業務に精通している場合や自分の仕事に対して過剰に自信を持っている場合に起こりやすい。
8)その他
・他人依存型評価 :どうせ2次評価者や調整者が評価し調整するのだから…という無責任な評価
・逆算型評価 :すべての被評価者の評価をした後で点数調整を行う評価
・感情型評価 :好き嫌いの感情で、好きな人には高い評価、嫌いな人には低い評価を付けてしまう評価
いかがでしょうか。誰もがどれかのバイアスに陥ったことがあると筆者は考えます。
かつ、ここでご紹介できたものはバイアスの全てではありません。
バイアスを取り除く方法はあるのか
では、面接においてバイアスを除去するにはどうすれば良いのでしょうか。
実は、アメリカ陸軍も上長選抜にあたって「認知バイアス」に悩まされています。
そしてさまざまな手法を検討した結果のひとつとして、面接者と上長候補者の間を黒いカーテンで仕切るという「ダブルブラインド面接」を実施しています*2。
この手法は、新卒採用にあたっては興味深い手法かもしれません。相手の表情が見えないことがバイアス除去につながる可能性があるからです。
ただ、数ある認知バイアスの中で、最も厄介なものがあります。
それは「自分はバイアスなど持っていない」と考えてしまうバイアスです。
こうした部分を指摘すると、バイアスについては無限の入れ子のようになってしまうかもしれませんが、解消方法があるとすれば筆者はこのように考えます。
それは、人事担当者が互いにメンバーの特性を知ることです。互いに面接しあうのも良いでしょう。
「バイアスを持たない人など存在しない」という前提に立ち、少しでも多くのフィルターを設けるのです。
また、「客観的な結果」を意識することが重要です。
ビジョンなき採用・評価に陥らないために
各種の人事面談、とくに新卒採用の場合「ビジネスの成果」がゼロの状態ですから、これまでどんな結果を残してきたのかはなかなか探ることができません。認知バイアスに陥りやすいシチュエーションといえます。
そこで、客観性を担保できる面接方法を取り入れてみるのも良いでしょう。「どのような人材が欲しいのか」を明確にし、面接担当者が客観的な指標を共有しておくのです。
例えば近年、面接の場で注目されているのが「STAR」と呼ばれるフレームワークです。これは、
Situation:「どのような状況で」
Task:「どのようなタスクを持ち」
Action:「どのような行動をして」
Result:「どのような結果をもたらしたか」
を軸に話を聞くというものです。
その人の「雰囲気」ではなく、その人が「どのようにものを考える人なのか」「どのように考えた結果、どのような行動に出るのか」といった思考回路や行動特性を見るのです。
また、「FFS理論」も注目されている人事戦略のひとつです。
人のさまざまな特性を「ポジティブ」「ネガティブ」という2軸ではなく、「凝縮性因子」「需要性因子」「弁別性因子」「拡散性因子」「保全性因子」といった種類に分けるというものです。それぞれの特性を持つ人は、他の特性が欠けているということでもあります。
相手の思考回路や特性が自社の理念や、求める行動特性に見合うものか。
あるいは、これまでになかった発想や行動特性を持つ人を新たな風として迎え入れるのか。
まず基本的な戦略を立ててから採用や面談にあたることも、バイアスに惑わされないひとつの方法になり得るでしょう。
2002年京都大学理学部卒業後、TBSに主に報道記者として勤務。社会部記者として事件・事故、テクノロジー、経済部記者として各種市場・産業など幅広く取材、その後フリー。
取材経験や各種統計の分析を元に多数メディアに寄稿中。
*1
「大津市 人事評価実施要領」総務省資料
https://www.soumu.go.jp/main_content/000611732.pdf p45-47
*2
「ハーバード・ビジネス・レビュー」 2021年2月号 p107